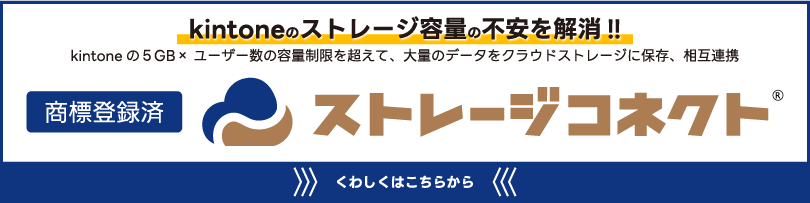業務の棚卸しから始めるDX 〜CapDo(キャップドゥー)サイクルで実現する効率化〜
はじめに

近年、企業の業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進において、さまざまなツールが注目を集めています。
たとえば、サイボウズkintoneによる業務アプリの内製化、monday.comによるタスク管理・プロジェクト可視化、そして今や欠かせない存在となった生成AIツールの導入。
これらは一見すると「入れるだけで効率化できる魔法の杖」のように思われがちです。
しかし実際には、どんなに優れたツールでも、自社の業務実態を把握していなければ、その効果を十分に発揮することはできません。
私たちキャップドゥー・ジャパンが現場で支援を行ってきた経験からも、成功する企業に共通しているのは「まず業務を棚卸しし、全体像を可視化する」という姿勢です。
本記事では、DXの第一歩としての「業務の棚卸し」の重要性、そこから生まれる改善の視点、そして私たちが大切にしているCapDoサイクル(Check → Action → Plan → Do)との関わりについて詳しく解説します。
業務の棚卸しとは何か
「業務の棚卸し」とは、現在の業務を一度立ち止まって洗い出し・整理・可視化することを指します。棚卸しという言葉は本来、在庫管理で使われるものですが、業務に当てはめると「どんな業務が、誰によって、どのように行われているのか」を把握する作業です。
業務棚卸しの目的
1.業務の重複やムダを見つける
2.属人化(特定の人しかできない業務)を明らかにする
3.本当に価値を生んでいる業務と、そうでない業務を切り分ける
4.改善の優先順位をつける
ここで重要なのは、棚卸しは単に「一覧表を作ること」ではない、という点です。
「見える化」した後に、改善の芽を発見することこそが棚卸しの真の目的です。
棚卸しのステップ

では、実際に業務の棚卸しはどのように進めればよいのでしょうか。
一般的には次のステップで整理します。
1.業務リスト化
部署・チーム単位で、日常的に行っている業務を洗い出します。ここでは「小さく分解する」ことがポイントです。
2.業務ごとのフロー可視化
洗い出した業務について、「誰が、何を、どの順で、どのツールを使って」行っているのかを図式化します。
3.課題発見
フローの中で「待ち時間が長い」「二重入力が多い」「承認に時間がかかる」など、現場で感じているボトルネックを抽出します。
4.優先順位づけ
発見した課題を「緊急性」と「重要性」でマッピングし、取り組むべき順序を決めます。
5.改善とツール選定のマッピング
「この課題はkintoneで解決できる」「これはmonday.comで見える化できる」「これはAIで自動化できる」と結びつけていきます。
このプロセスを通じて初めて、自社に最適なDX施策が浮かび上がってきます。
フローの棚卸し ― なぜ流れを可視化するのか
単なる業務リスト化では限界があります。そこで重要なのが業務フローの棚卸しです。
例えば「営業日報」という業務を取り上げましょう。
リスト化すれば「営業日報の作成」という1行で済みますが、フローで見ると次のようになります。
1.営業担当が日報を作成
2.上長が確認・承認
3.営業事務が集計
4.経営層が報告書として閲覧
この流れを可視化すると、承認に時間がかかる/集計が二重作業になっているといった課題が一目で分かります。
結果として、「承認フローを自動化できないか」「集計を自動化できる仕組みが必要だ」という改善案が生まれます。
フローの棚卸しは、課題を“見える化”するための強力なレンズなのです。
CapDo(キャップドゥー)サイクル 『現状把握から始める改善!!』

私たちキャップドゥー・ジャパンの社名にもなっている「CapDo(キャップドゥー)サイクル」。
これは、Check → Action → Plan → Doという順序で回す改善手法です。
一般的なPDCAサイクルとの大きな違いは、最初に「Check(現状把握)」から始める点です。
つまり「やってみて振り返る」のではなく、最初に棚卸し(Check)を行い、次に小さな改善(Action)を試し、計画(Plan)を立て、実行(Do)するのです。
この順序によって、現実に即した改善策を立案でき、机上の空論に陥るリスクを大幅に減らせます。「業務の棚卸し」はまさにこのCapDoサイクルの出発点にあたります。
棚卸しからツール導入へ 『具体的な事例』
kintoneの活用例
ある企業では、紙やExcelでの申請書が煩雑になっていました。棚卸しの結果、「承認に時間がかかる」「過去の記録が探しにくい」という課題が明確に。
改善: kintoneでワークフローを電子化し、過去データも一元管理することで業務効率が劇的に改善しました。
monday.comの活用例
別の企業では、プロジェクト進捗がブラックボックス化していました。棚卸しで「情報が担当者に閉じている」「全体像が共有されていない」と判明。
改善:monday.comのボードで進捗をリアルタイム共有し、会議の時間短縮と担当者間の連携強化を実現しました。
生成AIの活用例
また、生成AI導入では「定型文の作成に時間がかかる」という棚卸し結果が出た企業がありました。
改善:AIに下書きを任せ、人は最終チェックだけを行う仕組みに変えたところ、作業時間が半分以下に削減できました。
お客様と『共に歩む』姿勢
キャップドゥー・ジャパンの企業理念は『共に歩む』です。業務の棚卸しは、お客様と一緒に現場を見ながら行うからこそ効果があります。
「ITの専門家が一方的に診断する」のではなく、現場の声を尊重し、納得感を持ちながら改善を共創していく。
この姿勢が、単なるシステム導入にとどまらない「文化として根づく業務改善」を実現します。
まとめ

DXの成功は、最新のツールを導入すること自体ではなく、業務の棚卸しから始まります。
業務をリスト化し、フローを可視化し、課題を明らかにする。
そのうえで改善の優先順位を整理し、最適なツールを選定することが、効果的な業務改革につながります。
私たちキャップドゥー・ジャパンが重視する『CapDoサイクル(Check → Action → Plan → Do)』は、この「棚卸し=Check」を出発点に、現実的で持続可能な改善を進めていくフレームワークです。
●サイボウズkintoneで属人化や紙・Excel中心の業務を解消
●monday.comでタスク・プロジェクトを見える化し、連携を強化
●生成AIツールで定型作業を効率化し、付加価値業務に集中
これらを適切に組み合わせることで、業務改善のスピードと効果は飛躍的に高まります。
DXの最初の一歩は、CapDo.JAPANと共に!
私たちキャップドゥー・ジャパンは、「業務棚卸し」から始まり、kintone・monday.com・生成AIツールの導入支援と活用伴走まで一貫してサポートします。
業務効率化に本気で取り組みたいとお考えの企業様、ぜひCapDo.JAPANにご相談ください。

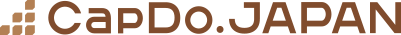
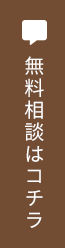

 クラウド豆知識
クラウド豆知識